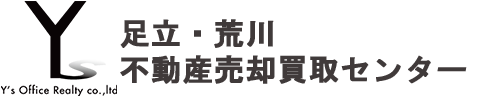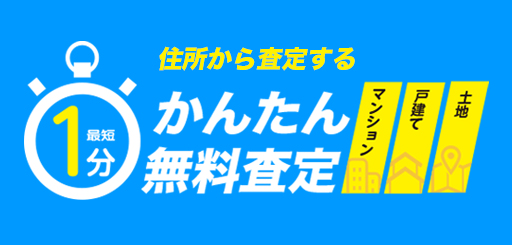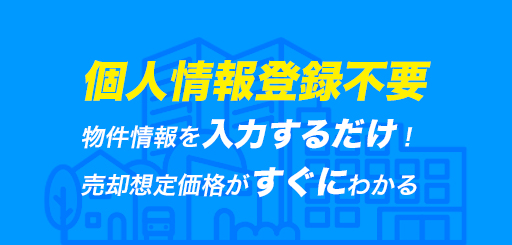■ 地価公示と相続税の関係
相続税の課税対象となる土地の評価額は、主に「路線価」または「固定資産税評価額」を基準にして決まります。
-
路線価は、毎年7月に国税庁が公表します。
-
路線価は、地価公示価格のおおむね 80%程度 を目安として決められます。
■ 令和7年地価上昇 → 路線価上昇 → 相続税評価額が増加
したがって:
-
令和7年の地価公示で「三大都市圏で上昇幅拡大、地方圏でも上昇傾向」とあることから、
-
令和7年分の路線価も、多くの地域で上昇する可能性が高いです。当然、都心の不動産価格上昇の流れはいわゆる下町地域とされる荒川区、足立区の地価上昇への影響も例外ではありません。
-
それに伴い、土地を含む相続財産の評価額が上がるため、結果的に相続税の負担が増える可能性があります。
■ 具体的な影響例
-
同じ土地を相続しても、評価時点の地価や路線価が高ければ、相続税額も高くなる。
-
特に都市部(東京・大阪・名古屋など)では、上昇幅が大きければ相続税額に大きな差が生まれる。荒川区、足立区も同様です。
-
地方部でも地価が回復基調にある地域では、以前は非課税だった土地が課税対象になることも。
■ 対応策や留意点
-
将来的な相続に備えた生前贈与の検討や、**不動産の活用(貸付など)**が節税対策になり得ます。
-
専門家に依頼して、**土地評価の減額特例(小規模宅地等の特例など)**を有効活用することが重要です。
■ まとめ
令和7年の地価上昇は、結果的に相続時の土地評価額を押し上げ、相続税額の増加につながる可能性があります。したがって、地価動向は相続税にも間接的ではあるが確実に影響を与えていると言えます。
相続された物件の対応には、経験豊富なワイズオフィスにぜひお声をかけて下さい。
ご一緒に最良の方法を考えて参りましょう。