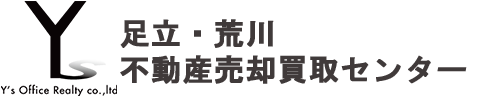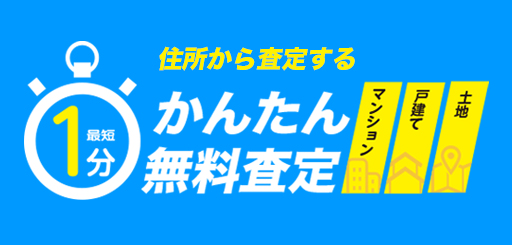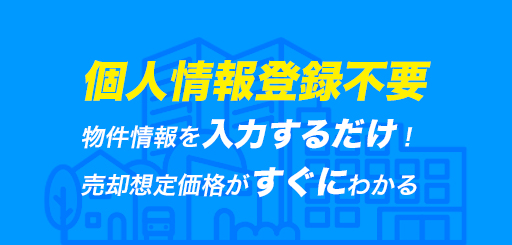相続した土地が接道しているのは「道路」なの?
先日、足立区・荒川区内の物件ではありませんが、このようなお問合せを頂きました。
ご自身で少しお調べされて、どのように対応したら良いかわからないとのこと・・・
-
建物再建築の際、接道要件の対象となるのはあくまでも「道路」である必要があります。
→ 今回の接道部分は「通路」であって「道路」ではないことが判明。 -
形状はコの字型をした一見「私道」のように判断できますが、調査の結果は位置指定もされておらず、「私道」でもなく無論「公道」でもありませんでした。一体、どのように規定されているのか・・、建物再建築の要件を満たすことはできるのであろうか。
-
ご質問者の方の不安は増すばかりです・・
-
結果は・・建築基準法43条第2項第2号を適用する必要があるが、区役所と協議する必要がある。
→ 申請して協定道路の認可を得て、再建築可能とする方法がある。 -
ただし、簡単ではありません。補足すると、
→ 「協定道路」としての成立ができていない状況にあることも判明しました。
→ この通路に接してはいるが、他の道路にも接道している土地所有者が、
敷地の一部を供出しないとならないため協定に同意していない。(位置指定道路にできない) -
区役所側も十数年前より、この状況を承知しており解決したい意向である。
■ 建築基準法 第43条第2項第2号とは?
通常、建築物を建てるには、建築基準法第42条に基づく幅員4m以上の「道路」に2m以上接している必要があります。例外的に第43条第2項第2号では、接道義務を満たさない場合でも、以下のような条件を満たせば特例的に建築を認めることがあります。ただし、基本的に幅員を含めた現況が「道路」としての要件を満たしていることが前提です。
-
関係者(共有持ち分所有者)の協定(協定道路等)により「通行可能性」が確保されている。
-
建築審査会の同意を得た上で、例外的に許可される場合がある。